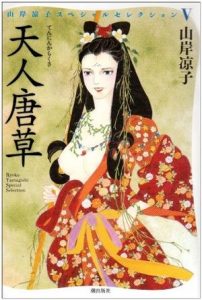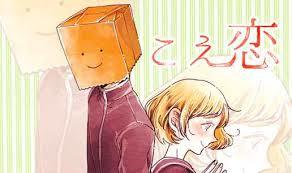こんにちはtez200000です。
昨今はスマートフォンの普及により、電子書籍という物が台頭してきました。
私自身、小説、専門書、ビジネス書などは書き込む事が多いため、紙の本を購入するのですが、漫画に関していうと最近はもうほとんど電子書籍での購入になっています。
時代の波にサーフィン感覚で乗りまくっているわけですね。
漫画は巻数が多くなってくるとどうしても場所を取ってしまいますよね。
さらに外出の際のちょっとの隙間時間でも気軽に読めてしまうという点も電子書籍の良さです。
そんな電子書籍マニアになりつつある私なのですが、案外読みたい漫画というものは電子書籍にされていないなんてことが多いんですよ。
おそらくみなさんもネットサーフィンや友達との会話の中で気になる漫画と出会って、本屋に行く時間も惜しんでアマゾンで電子書籍を探してみたのにもかかわらず、電子書籍化されていなかった。
なんて、悲壮感漂う体験をしたことあるんじゃないでしょうか。
自身の中でそんな体験も多くなってきたので、気にしているとどうやら電子書籍化されないのは出版社の都合などではなく、漫画家さんの漫画に対する考え方などから電子書籍化していないようなんですよ。
そしてそれを深掘りしていくと「なるほど」と思妙に納得させられる、漫画家さんたちの漫画に対する「哲学」が多数あることを知りました。
今回は電子書籍化していない漫画家さんたちをまず簡単にご紹介し、その後電子書籍されないその理由を語っている漫画家さんや編集者の意見をご紹介したいと思います。
電子書籍にならない有名漫画家まとめ
井上雄彦さん
代表格といえばこれまで、数多くの大ヒット作を生み出し続けている井上雄彦さんです。
私自身も崇拝するほどの大好きな漫画家さんです。
現在もヤングジャンプで「リアル」、Dモーニングで「バガボンド」と二つの連載を抱えております。
大好きな漫画家さんなので彼を取り上げたドキュメンタリーなども見ているのですが、彼の話している姿はモニター越しですら、精神の成熟度合いが伺えます。
精神の域はもうすでに厳しい修行を終えた僧の域に達しているのではないかと思うほどです。
浦沢直樹さん
「YAWARA!」や「20世紀少年」、「MONSTER」など数々のヒット作品を打ち出しているこちらも大人気作家です。
現在もDモーニングで「BILLY BAT」を掲載しています。
さらにNHKでは「漫勉」という漫画家さんを取り上げる番組もやっており、様々な漫画家さんの漫画に対するこだわりに迫っています。
その「漫勉」を見ると、漫画家さんたちは一コマ一コマに決して妥協することをなく思いを込めて書いていることがわかります。
森川ジョージ
「はじめの一歩」で有名な作家さん。
一度は60巻までは電子書籍化されましたが、その後作者の意向のため配信されなくなりました。
山岸涼子
「天人唐草」、「夜叉御前」など人間の深層心理に切り込む女性人気作家。
天人唐草を読んだ時はこれまでの人生を一変させられるような多くの衝撃をうけました。
漫画家たちが電子書籍にしない理由
浦沢直樹さんの哲学
本人は自身を未だに紙媒体でやっている原始人と揶揄しつつも、電子書籍にしない理由をいくつか語っています。
まず、小さいスマホの画面で読んでほしくないという点です。
たしかに細かい表現などはスマホだと分かりにくくなってしまうかもしれませんね。
次に、漫画は見開きの状態でどのように見えるかということを演出します。スマホだと1ページになってしまうので漫画の演出に適さないという点です。
さらに現在のIT化されたことによる、無料漫画にも苦言を呈していて、
浦沢直樹さん自身幼少期自分の単行本は250円くらいで当時のとても買えるものはない代物という印象だったそうです。
そして、その単行本を眺めながら「いいなぁ、お金が貯まったら、あの単行本が欲しいなぁ」と憧れがあったそうです。
「タダで見る」ということは、幼少期自分が持っていた漫画に対する憧れがなくなってしまうことに危機感を覚えているようです。
この意見は、熱い思いで漫画と向き合っている浦沢直樹さんだからこその意見のように感じます。
読者である私もこの思いに答えるかのように真摯に向き合わねばと考えさせられます。
さらに持論を展開していて、無料で読んでいる限り読者と漫画家は対等な関係になることはできず、文句を言う権利がそこにはなくなってしまうと述べています。
もちろん、漫画を購入した読者はいくら文句を言う権利があるという前提でです。
浦沢さん自身もなにか意見を言う際はものを自分で買うことに決めているそうです。
ものを作ることを生業としている彼の哲学ですね。
「モーニング」編集長島田さんの考え方
浦沢直樹さんと井上雄彦さんの編集を務める「モーニング」編集長の島田英二郎さんは、電子書籍化されない理由を
電子はあくまで電子であって紙の読み味は再現できない。
さらに電子書籍は1話20ページの「2Dのエンターテイメント」を動画じゃなくて静止画で楽しんでもらうための、滑らかさ・見やすさの追求であって、紙の再現とはちょっと違うんです。
たとえば「めくる」といった身体的行為に代表される“紙にしかないもの”は大事で、それがマンガの面白さ・読み味の中の幾ばくかを担っているのは確かなんです。でもそれを抜いたら漫画が成立しないとは限らない。一方、それを抜いたら作品として成立しないと作者がお考えなら、その作品は電子化することはできないでしょう。以上、島田個人の考えですが。
と語っています。
こちらもなるほどと納得させられます。
また、島田さんは「作品は生き物なので、電子で読む事がこれからどんどん広がることによって作品自体もこれまでとは違った電子書籍に向けた作り方に変わってくる」と述べています。
編集者ならではの視点で漫画という媒体を深い目線でみていることがわかります。
まとめ
自身はこれまで、漫画を電子書籍化することに大賛成でしたが、漫画好きである以上、作者の思いにそって読むことが正しいのではないかと思いました。
なので、電子書籍化しない漫画家さんたちの漫画はその思いを汲み取って、文句を言わず漫画を紙媒体で読んでいこうと思います。